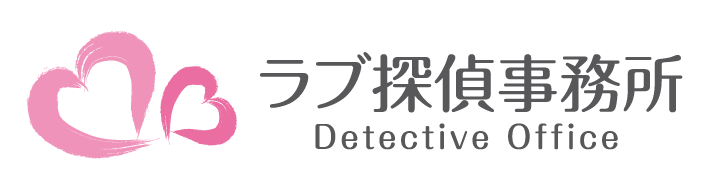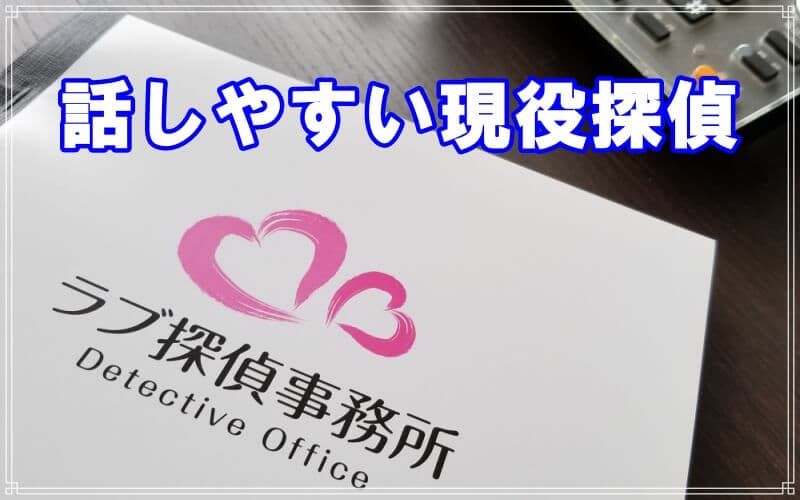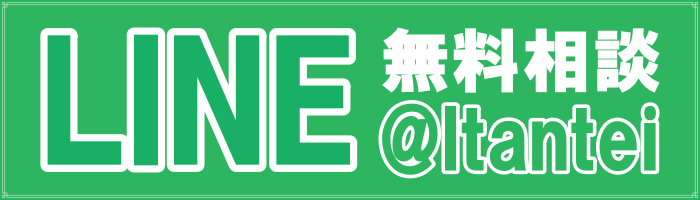ラブ探偵事務所の現役探偵「エル」です。
今回も「探偵エルのひとり言」ブログでは、探偵事務所や興信所などの探偵調査員が日々の調査業務や浮気調査・素行調査などでも使っている探偵専門の隠語に焦点を当て「探偵用語のいろは~其の参~」というタイトルで探偵用語の一部をご紹介していこうと思います。
「探偵用語のいろは」シリーズの続編となる探偵用語のご紹介なので興味本位でも読んでい頂けたら嬉しいです。
初めて相談や依頼をする現実の探偵事務所や興信所という未知の会社がどの様なものなのか事前に知って頂こうという思いで書いています。
探偵事務所や興信所への相談前に少しだけお役に立てれば幸いです。
探偵の専門用語や隠語をご紹介

どんな業界にも、専門的な用語や隠語などは多数ありますよね。
もちろん探偵業界にも専門用語や隠語の類は多数存在します。
前回と前々回のシリーズに引き続き、「探偵用語のいろは~其の参~」として新たな探偵用語をご紹介したいと思います。

その他の「探偵用語のいろは」シリーズはこちらをご覧ください。
千葉県松戸市新松戸のラブ探偵事務所現役探偵ブログ「探偵エルのひとり言」より新着情報のお知らせです。ラブ探偵事務所の現役敏腕探偵エルがあなたの質問に答えていきます。本日は探偵が日常業務や浮気調査などでも使っている隠語の一部について「探偵用語のいろは~其の壱~」として紹介しているのでリラックスタイムなどに読んでみてください。
千葉県松戸市新松戸のラブ探偵事務所現役探偵ブログ「探偵エルのひとり言」より新着情報のお知らせです。ラブ探偵事務所の現役敏腕探偵エルがあなたの質問に答えていきます。本日は探偵が日常業務や浮気調査などでも使っている隠語の一部について「探偵用語のいろは~其の弐~」として紹介しているのでリラックスタイムなどに読んでみてください。
千葉県松戸市新松戸のラブ探偵事務所現役探偵ブログ「探偵エルのひとり言」より新着情報のお知らせです。ラブ探偵事務所の現役敏腕探偵エルがあなたの質問に答えていきます。本日は探偵が日常業務や浮気調査などでも使っている隠語の一部について「探偵用語のいろは~其の肆~」として紹介しているのでリラックスタイムなどに読んでみてください。
千葉県松戸市新松戸のラブ探偵事務所現役探偵ブログ「探偵エルのひとり言」より新着情報のお知らせです。ラブ探偵事務所の現役敏腕探偵エルがあなたの質問に答えていきます。本日は探偵が日常業務や浮気調査などでも使っている隠語の一部について「探偵用語のいろは~其の伍~」として紹介しているのでリラックスタイムなどに読んでみてください。
探偵業界の専門用語と隠語の違い
本格的な調査に出る前に尾行・張り込み・聞き込み・撮影など、調査員としての基本スキルを習得する事はもちろんのこと、専門的な用語も覚えなければいざという時に調査員間でコミュニケーションが取れず、調査には関われません。
会話の内容に専門用語や隠語が含まれているため、初めて聞く人は意味を理解できません。
でも、専門用語や隠語ができた経緯として意味合いがあるのはご存知でしょうか?
まず専門用語からお伝えすると、短縮したり、略したりするのは業務において「使う人が使いやすい」という点が優先されているからなんです。
ずらっと長い正式名称より、短縮した専門用語の方が業務を行う際、非常に呼びやすいという理由で言葉に変化したようです。
隠語については専門用語とは少し違い、全く違う呼び名を採用することが多いです。
それは「直接他人に聞かれても理解できない」という点が重視されているため、専門用語のように短縮したり、略したりするのではなく、全く違う呼び名に変化したようです。
また、探偵業の専門用語や隠語には警察関係の専門用語や隠語が多数含まれています。
これは警察は刑事事件、探偵は民事事件について動くと考えてもらった方が解りやすいかもしれません。
それに、尾行・張り込み・聞き込みなど警察も探偵も似ている業務があるということも影響しているんですね。

皆さんのお仕事は何ですか?どんな業界にも、専門的な用語や隠語などは多数ありますよね。
探偵業界にも専門用語や隠語の類は多数存在しているので、ここからはさらに応用的な探偵用語をご紹介していきますね。
探偵用語のいろは其の参

契約書類関連の探偵用語
「探偵業の業務適正化に関する法律」で定められており、探偵業者が探偵業務の契約を締結する際、必ずご依頼者様へ調査契約の詳細を記載した書類を交付することが義務付けられている。
この書面を発行しない探偵業者である場合、行政処分の対象となる。
「探偵業の業務適正化に関する法律」で定められており、探偵業者が探偵業務の契約を締結する前に、必ずご依頼者様へ説明し、控えを渡すことが義務付けられている。
この書面を発行しない探偵業者である場合、行政処分の対象となる。
「探偵業の業務適正化に関する法律」で定められており、探偵業者が探偵業務の契約を締結する際、必ずご依頼者様から探偵業者へ調査内容に関して違法に利用しないという「誓約書」を記載してもらい、控えを渡すことが義務付けられている。
この書面を発行しない探偵業者である場合、行政処分の対象となる。
「探偵業の業務適正化に関する法律」で定められており、探偵業者が探偵業務の契約を締結する前に、必ずご依頼者様へ調査金額のお見積書として合計金額を記載した書類を交付することが義務付けられている。
この書面を発行しない探偵業者である場合、行政処分の対象となる。
調査関連の探偵用語
夜間に車両で尾行中、対象者が乗車している車両に気付かれないよう、ヘッドライトやフォグランプの切り替えを行うこと。
ライト見え方を変化させて、追尾している車両を特定されずらいなどの視覚効果となる。
調査対象となる現場へ出動すること。
調査対象となる現場に到着すること。
内通者・部外者などから情報提供を得ること。
目撃証言や聞き込み証言のこと。
現在進行形で起こっている物事のこと。
現場の状況などを説明する際に用いられる。
現場で起こっている事柄を目で見て認識すること。
状況を説明する際に用いられる。
探偵業者によっては、黙認・目視などと呼ばれることもある。
調査対象となる人物の居住先となる場所のこと。
調査対象となる人物を尾行をして居住先を特定すること。
浮気相手の調査や、債務で逃げている相手に対しての調査などに多い。
探偵業者によっては、ヤサ尾け・ヤサ割りなどと呼ばれることがある。
調査対象となる人物を尾行をして勤務先を特定すること。
信用調査や、債務で逃げている相手に対しての調査などに多い。
探偵業者によっては、勤務割りなどと呼ばれることもある。
調査対象者となる人物の顔を確認すること。
調査中に初めて見る人物のこと。
調査対象者となる人物の自宅周辺や立寄り先などの状況を事前に調べておくこと。
調査対象者となる人物の自宅や会社に身分を隠して訪問すること。
推測や憶測ではなく、確実な証言や証拠を収集すること。
探偵業者によっては、裏付けや裏を取るなどと呼ばれることもある。
裏取りを目的とした調査のこと。
探偵業者によっては、裏付け調査やアリバイ調査などと呼ばれることもある。
対象となる項目に対して調査すること。
または、一度行った調査で再度調査し直す場合などに用いられる。
確実な証言や証拠が確認できたこと。
探偵業者によっては、足などと呼ばれることもある。
疑わしい人物だったが調査を行った結果、疑わしくない人物であると判断できたこと。
当初から疑わしい人物ではない場合、シロとは呼ばない。
疑わしくない人物だったが調査を行った結果、対象人物であると判断できたこと。
当初から疑わしくない人物の場合、クロとは呼ばない。
調査員として新人のこと。
動きが俊敏な人物のこと。
盗聴器を表す隠語のこと。
バグ(Bug)とは英語で「虫」を意味する。
いつまにか建物内へ侵入している小さな虫という意味で名付けられた。
探偵業者によっては、虫と呼ばれることもある。
電波形式がデジタル電波を使用する携帯電話を盗聴器に改造して盗聴を行う手法のこと。
デジタル電波の「デジタル」をとってそう呼ばれている。
基本的な使用方法は携帯電話と一緒で、電波が圏外でなければ世界中どこからでも設置した場所を盗聴することが可能となる。
遠距離の盗聴なども、デジタル盗聴や遠距離盗聴と呼ばれる場合が多い。
自宅の固定電話のみを盗聴することに特化した手法のこと。
家屋内のある対象世帯の電話配線に盗聴器を接続することで、通話した時の会話の内容を盗聴する。
マンション・アパートなどでも、家屋建物の外壁部の保安器に盗聴器を仕掛けられるため、宅内に侵入しなくても通話内容を盗聴できる。
※コードレス電話機の子機で会話した内容が漏れている場合はここに該当しない。理由としては、親機と子機の間でやり取りしている電波を傍受されているだけなので子機をしようせず、親機のみを使用すれば防げるからだ。
盗聴したい建物の窓ガラスにレーザー光線を照射し、反射したレーザーを受信して音声へ変換することで室内での会話を聴くという盗聴手法のこと。
室内の音声が微弱な振動となって窓ガラスに伝わり、レーザー光線に振動を与えるという仕組みなのだが、機材が高額であり、立地条件などに影響を受けやすいため、実用的に使用されることはほとんど無い。
自宅や会社などに設置されている固定電話回線に特殊な盗聴器を取り付ける手法のこと。
使用中のみ盗聴される電話盗聴器とは別で、取り付けられた電話機は永遠と通話状態となり、受話器から会話内容も漏れ続ける。
現在、一般的に販売されておらず、入所も困難となる。

皆さんどうでしたか?今回も探偵専門の隠語「探偵用語のいろは~其の参~」としているので初めて知る探偵用語も多かったのではないでしょうか。
次回も「探偵用語のいろは」の続編としてもうさらに踏み込んだ複雑な探偵用語などもご紹介していきたいと考えていますので楽しみにしてくださいね。
各種無料相談
電話で無料相談

LINEで無料相談
メールで無料相談
このご相談フォームからラブ探偵事務所へ各種調査の無料相談・無料お見積り依頼ができます。千葉県松戸市のラブ探偵事務所はJR新松戸駅徒歩3分に無料相談室を完備しており探偵業界最安値の料金体系です。